服部緑地
行こうよ!
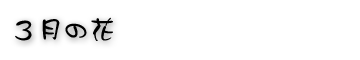
見頃:12月中旬~3月下旬

花言葉は控えめな愛。冬の寒さに耐えて咲く姿にちなんだものと思われます。日本、中国、東南アジアを中心に約100種あるそうです。
見頃:1月中旬~3月中旬

晩冬から早春にかけて、白や紅色を咲かせるバラ科木、古くから人々に親しまれており、「万葉集」や「古今和歌集」などの詩歌に数多く詠まれています。春告草、匂草ともよばれます。
見頃:1月下旬~3月中旬

別名ナルキソス。ギリシア神話で水面に写る自分の姿に鯉をした美青年に由来します。黄と白の小さな花弁、すっくと立つ姿はどこか高貴で気高い雰囲気。地中海沿岸原産で、シルクロードを通じて日本にやってきたそうです。
見頃:11月中旬~3月上旬

白やピンクをつけるツバキ科の常緑小高木。江戸時代から栽培されており、東雲や富士の峰など様々な品種があります。
見頃:11月中旬~3月中旬

中世ヨーロッパではバターやチーズの色づけ、調味料などにも使われたそうです。 語源は、黄金色が杯に似ていることに由来しているそうです。
見頃 :3月下旬~4月上旬
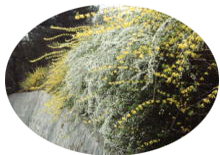
しなやかな枝に雪のような花をつけることから名づけられたと言われています。花言葉は殊勝。寒い冬をじっと耐え忍びながら新芽を育む、そんなけなげな姿からつけられたのでしょう。
見頃 :3月下旬~4月上旬

モクセイ科の落葉低木。 長い枝の先に黄色をつけます。観賞用と共に薬用の歴史も古く、漢方では果実を熱性病の初期治療などに用います。
見頃 :3月下旬~5月上旬

早春、葉に先立って、香りの強い花をつけます。古くは「田打ち桜」とも呼ばれ、農作業を始める目安にされたそうです。
見頃:3月下旬~4月上旬

語源はラテン語のアザロス(乾燥)。もともと乾燥した土地を好むことから名づけられたそうです。中国南部原産のシナノサツキと日本原産のサツキをかけ合わせたもので、赤や白、または紅白混じりあった花を咲かせます。
見頃:3月下旬~4月上旬

日本の春を代表する花木。 バラ科の落葉高木・低木で、一般的に花びらは桃色ですが、淡い黄緑色のウコン、ギョイコウという種類もあります。